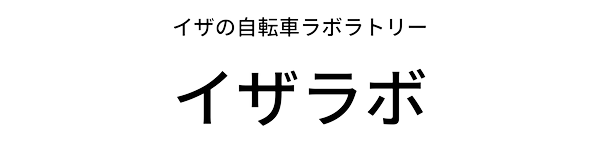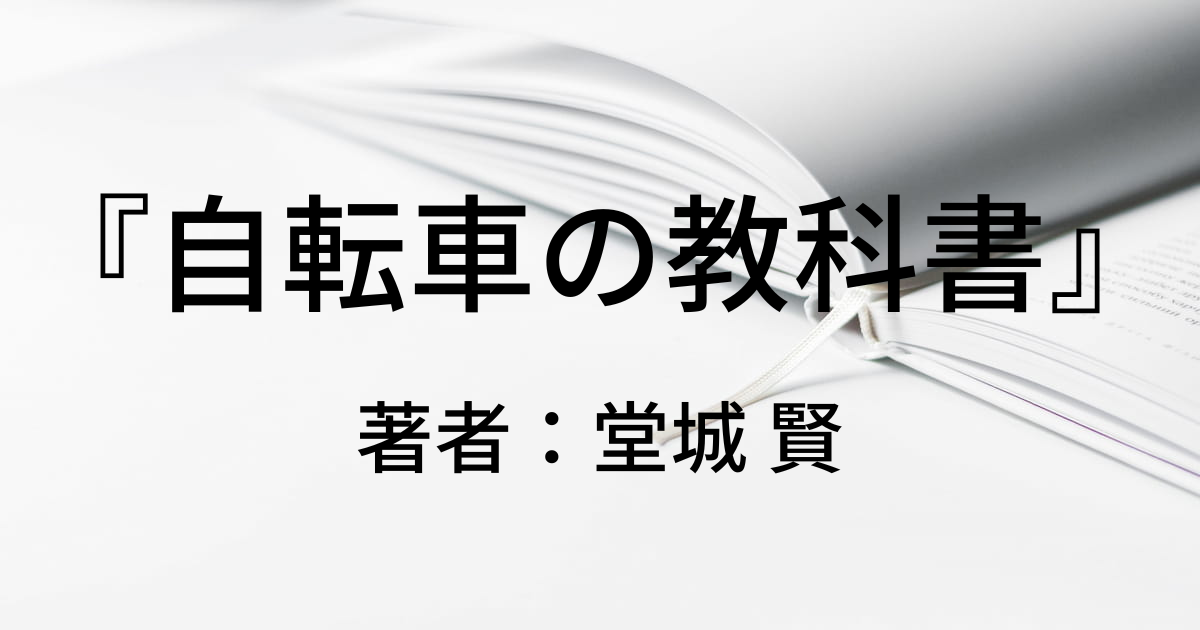ロードバイクの姿勢やポジションについては、いろいろな意見があります。
人によっては違うこというので、どれを参考にしていいかわからないですよね。
そこで良いヒントを与えてくれる本が『自転車の教科書』(著者:堂城 賢)。
この本では「おじぎ乗り」という乗り方を教えています。
「おじぎ乗り」によって楽に速く、安全に走ることを目的とする内容です。
ロードバイクに5年以上乗っている僕でも、新たな発見があり参考になりました。
イラストや実践方法が載っていて分かりやすいので、初心者にはうってつけの内容です。
まさに「自転車の教科書」。
この本では
- 正しい自転車の乗り方
- 正しい荷重移動
- ペダリングや上りなどの基本的なテクニック
- 練習方法
を学ぶことができます。
『自転車の教科書』は、マウンテンバイクプロライダーの堂城 賢(たかぎ まさる)さんの経験が詰め込まれています。
2013年に発売された本ですが、自転車の基本的な乗り方は変化しないため、現在でも十分参考になる本です。
そこで今回は『自転車の教科書』を読んで、僕なりの解釈を説明していきます。
「おじぎ乗り」は背中をまっすぐにする姿勢
大前提として「おじぎ乗り」という乗り方を推奨しています。
「おじぎ乗り」とは、背中をまっすぐにしたおじぎの姿勢で乗ること。
ポイントは
- 股関節から身体を曲げる
- 背中を丸めない
「おじぎ乗り」の最大のメリットが、自然に前足に荷重がかかり、後ろ足の荷重が抜けることです。
これによりペダルを踏み込まずにクランクが勝手に回る、理想的なペダリングが実現できます。
著者の堂城さんはこれを「夢の永久機関」と呼んでいるそう。笑
他にも「おじぎ乗り」には
- バランスが取りやすい
- 衝撃を吸収しやすい
- 安定しやすい
などのバイクコントロールや安全性に関わる点でも、メリットがあります。
ペダルの基本の位置は「1時7時」
本書の中で頻繁に出てくる用語が「1時7時」。
これはペダルの位置のことで、前足が1時で後ろ足が7時の位置ということです。
ペダリング時は、7時の足の荷重が抜けて1時の足に荷重されると、クランクが自然に回る「夢の永久機関」の出来上がりです。
また下りやカーブ、止まるときもペダル位置は「1時7時」。
この位置にペダルをするのは、いつでもペダリングができるためと、衝撃吸収ができるため。
「1時7時」は基本のポジションということでしょう。
荷重移動は超重要
マウンテンバイクプロライダーの堂城さんだからこそ、荷重を大切にされているようです。
正しい荷重移動や「おじぎ乗り」をする意味が、イラスト付きでとても詳しく説明されています。
堂城さんは荷重移動の定義として
荷重移動とは足の裏の三点に感じる荷重を前後に移動させることである
第二章 2 最重要 やまめの学校式「荷重移動の定義」より
と述べています。
足の裏の三点は、かかと、拇指球、親指のこと。

この三点は足の内側にあり、荷重をかけるためには足がワイドスタンスになります。
つまり正しい荷重移動とは、ワイドスタンスで足裏の内側に荷重をかけた状態で、足の裏の三点の荷重を前後に移動させること。
この正しい荷重移動ができると、自然と後ろ足の荷重が抜ける楽なペダリングができるのです。
これが「おじぎ乗り」で楽に速く乗るための、最重要事項でしょう。
荷重はロードバイクに乗っているだけでは、意識しづらい部分。
「ロードバイク乗りは、MTBがいい練習になる」といわれる所以ですね。
ワイドスタンスにするには
ワイドスタンスにするために、Qファクター(左右のペダルの間隔)を広くしなければいけません。
Qファクターを気にする方は少ないですが、見直したほうがいいかもしれませんね。
自転車だけでは脚力、体力不足
自転車は地面からの衝撃や反発が少なく、負荷が低い。
そのため自転車しかやってない人は、脚力や体力が不足していることが多いとのこと。
確かに「あの人は筋力不足だろうな」と思う方はけっこういますよね。笑
自転車に必要な身体作りとして
- 足首を柔らかくする
- 背筋を鍛える
- おしりの筋肉を鍛える
- 回復力の高い心臓を作る
これらをオススメされています。
1、ストレッチで、足首を柔らかくする
足首が硬いと、後傾した乗車姿勢になるためNGとのこと。
またペダリングも悪くなるし、衝撃吸収もできません。
柔らかくするためには、ストレッチボードやPNFストレッチをオススメされています。
2&3、正しく歩いて、背筋&臀筋を鍛える
正しく歩くことで正しい身体が作れるとのこと。
正しく歩けば、背筋や臀筋も鍛えられます。
正しい歩き方とは、背筋を伸ばして立ち、拇指球に荷重がかかり、後ろ足の荷重が抜けた状態。
先ほど説明した「おじぎ乗り」と同様の姿勢です。
つまり正しく歩くことは、ロードバイクにそのまま活かせる練習というわけです。
さらにオススメされているのがノルディックウォーキング。
ポールを持って歩くスポーツです。
ノルディックウォーキングは全身の筋肉の90%ほど使う全身運動。
また理想のウォーキングフォームを身につけるのに最適。
ただ歩くよりも良いトレーニングですね。
4、インターバルトレーニングで、回復力の高い心臓を作る
回復力の高い心臓は、心拍が上がっても少し休めばすぐ元の心拍に落ち着く心臓のこと。
これを鍛えるためには、インターバルトレーニングが必要。
初心者や趣味でやっている人には「スロー・インターバルトレーニング」を推奨しています。
「スロー・インターバルトレーニング」とは、運動中に「こまめに止まること」。
運動の強度は関係ありません。
正直「スロー・インターバルトレーニング」は、本当に初心者か、速さを求めない方向けの練習だと思います。
強くなるためにはある程度の強度が必要になってくるわけで。
ただ「高強度で無理をすると自転車のフォームが崩れる」という点は激しく同意ですね。
室内トレーニングでは強いのに、実走するといまいち速くない人が典型例。
フィッティングは「その人の理想の姿勢に自転車を合わせること」
フィッティングは「その人の理想の姿勢に自転車を合わせること」であり、自転車に人が合わせてはいけません。
人に合わせてフレームやパーツを選びましょう。
大きめなフレームを選べ
大きめなフレームを薦められています。
それは「おじぎ乗り」では、大きめなフレームのほうが適正ハンドル位置を出しやすいため。
サイズが極端に小さくなければ、素材や重量はなんでもいいとのこと。
ポジションの定義
ポジションとは股関節から身体を折り曲げたおじぎをして、足の裏は拇指球に体重が乗った状態を作り、手を振り子のように振ったところにハンドルがある。それだけです。
第四章 2 姿勢ができればポジションは簡単 より
このときの姿勢に、自転車のポジションを合わせます。
ハンドル位置、サドル位置、クランク長を合わせる
ハンドル位置
ハンドルは「おじぎ乗り」をした時に、手を振り子のように振った軌道にブラケットと下ハンの位置に合わせる。
サドル位置
サドルの前後位置は、ハンドルと同じで「おじぎ乗り」をした時に、おしりがある位置。
サドルの高さは、足を7時の位置にした時に、一番楽な膝の曲がりになるところで合わせる。
クランク長
正しいフォームができるまでは、こだわらなくて問題ない。
正しいフォームができてきたら、柔軟性に合わせて長さが自然に決まる。
ポジションは筋力や柔軟性しだい
フォームの上達や筋力、柔軟性の向上などで、ハンドルやサドル位置、クランク長などのポジションは変わります。
自分の成長に合わせてポジションを工夫し、変えていくことが重要。
「考えるな、感じろ!」とのこと。笑
基本テクニック
上りや下り、ダンシング、コーナリング、ブレーキングの基本テクニックについてです。
結構なボリュームなので、ポイントだけ触れていきます。
上りは浅いおじぎで
・急勾配では、浅いおじぎでお尻をサドルの前に移動 → 股関節が窮屈にならないため
・緩斜面では、ある程度深いおじぎでもOK
・スピードが落ちるときは変速せず、ダンシングなどで勢いをつけて、それを「1時7時」の脱力ペダリングでキープ。
下りは低い姿勢で
・深いおじぎでお尻を後ろに移動 → 身体が前に持っていかれるのを防ぐため
・下ハンをもつ → ブレーキングしやすいため
・足の位置は「1時7時」
ダンシングは自転車をゆらす
・自転車を左右にゆらす → バランスが取れて安定するため
・ハンドルは押し引きではなく回す → 足の回転を止めないため
コーナリングは両足の力を抜く
・両足の力を抜く → 衝撃吸収のため
・サドルにしっかり座る
・足の位置は「1時7時」
※外足を伸ばした外足荷重だと、滑った際に外足を軸にして身体が投げ出せれるので、絶対にNG
ブレーキングも「おじぎ乗り」
・前後のブレーキは5対5でかける
・姿勢は「おじぎ乗り」 → 安定するため
・足の位置は「1時7時」
技術習得には反復練習が重要
基礎技術が足りていない人が多い。
自転車には、技術を身につけるための「反復練習」が必要とのこと。
反復練習をして無意識にできるようになることを目指しましょう。
フラットペダルのすすめ
正しい「おじぎ乗り」では後ろ足に荷重しないため、ビンディングペダルはなくても問題なし。
むしろ初めは、フラットペダルで練習することをオススメされています。
フラットペダルで練習するメリットは、足の裏の荷重位置が分かりやすいことと、安全なこと。
僕は通勤でフラットペダルを使っていますが、スタンス幅を変えたり、荷重位置を変えられるので良い練習になってます。
-

-
ビンディングペダルはいらない?必要な人と不要な人は?
続きを見る
「宿題」で技術を磨きましょう
具体的な練習方法を「宿題」というかたちで解説しています。
- 宿題1:ケンケンしてごらん
- 宿題2:7時の横に足をつこう
- 宿題3:足をつかずに止まれますか?
- 宿題4:8の字練習
簡単だけれども、重要なトレーニング内容です。
「宿題」をやる理由やコツも書かれているので、確認しながら練習するといいでしょう。
解釈は読み手次第
本書の内容は、堂城さんの深い経験から書かれています。
納得感があり一見すべてが正解に思えてしまいますが、科学的に正しいか、万人にすべて当てはまるかは別の話。
(もちろん堂城さんが嘘をついているわけではありませんよ。笑)
しかし参考になるところや、僕自身が実践して効果があった部分もたくさんあります。
今回の解説は『自転車の教科書』を読んでの、僕なりの解釈です。
経験や考え方によって、重要な部分や解釈の違いがでます。
また本書は内容が濃いので、1回読んだだけでは理解できない部分もあります。
何度か読み返したり、気になった時に確認するといいでしょう。
初心者はもちろん、上級者でも読んで得られるものが必ずあります。
『自転車の教科書』は、サイクリストが1回は読むべき良書です。
続編もあるので『自転車の教科書』がハマった方は、こちらもどうぞ。